「不動産開業で必要な供託金とは?」
「供託金の金額はいくらかかるのだろう?」
「なるべく費用はおさえたい」
不動産業界への参入を考えている人であれば、このような疑問を抱えているのではないでしょうか。
不動産開業には多くの準備が必要ですが、供託金の納付も重要な要件のひとつ。
しかし供託金の種類・金額・納付方法については知らないことも多いでしょう。
そこで本記事では、おもに以下の内容を解説していきます。
- 不動産開業における供託金の必要性
- 営業保証金と弁済業務保証金分担金の特徴やメリット
- 供託から開業までの流れ
- 供託金の選び方と注意点
この記事を読むと、不動産開業に必要な供託金について理解を深められ、開業の準備をスムーズに進められるようになりますよ。
目次
不動産開業では供託金の支払いが義務づけられている

宅地建物取引業法(以下、宅建業法)では、すべての宅建業者に供託金の預け入れが義務づけられています。
供託金が必要とされるおもな理由は「消費者保護」です。
不動産取引は高額な取引が多く、トラブルが発生した場合に消費者が大きな損害を被る可能性があります。
そのため、万が一の際に消費者への賠償を確実に行えるよう、あらかじめ一定額を預けておく仕組みが設けられているのです。
具体的には、以下のようなケースで供託金が活用されます。
- 不動産会社の債務不履行による損害賠償
- 売買物件に重大な欠陥があった場合の補償
- 不動産会社の倒産時における消費者への弁済
国土交通省の統計によると、2023年度の宅地建物取引業者数は約13万社です(※1)。
これだけ多くの業者が存在するなかで、供託金制度は消費者が安心して取引できる環境を整える重要な役割を果たしています。
(※1)出典:国土交通省「令和5年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について」令和6年9月30日
営業保証金と弁済業務保証金分担金の違い

供託金には以下の2種類があり、どちらか一方を選択して納付する必要があります。
種類 | 詳細 |
営業保証金 | 法務局に供託するもの |
弁済業務保証金分担金 | 保証協会に納付するもの (保証協会を通じて法務局に供託される) |
順番に詳細を見ていきましょう。
営業保証金の特徴
営業保証金は、宅建業者が直接「法務局」に供託する保証金で、金額は以下のように定められています。
対象 | 金額 |
主たる事務所(本店) | 1,000万円 |
その他の事務所(支店など) | 1拠点につき500万円 |
出典:e-Gov 法令検索「宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)」
たとえば、
- 本店:1店舗
- 支店:2店舗
をもつと、必要な営業保証金は「合計2,000万円(1,000万円+500万円×2)」です。
営業保証金の特徴としては、以下の点があげられます。
- 現金だけでなく、有価証券での供託も可能
- 供託先は最寄りの法務局
- 供託後は免許権者への届出が必要
営業保証金のメリット
営業保証金のメリットは、開業までのスムーズさです。
保証協会への入会が不要なため、入会審査の期間や手続きの煩雑さがなく、免許通知を受けたその日に供託手続きを行い、スムーズに営業を開始できます。
また、開業前に用意しなければならない資金は高額ですが、保証協会の年会費や各種費用が一切発生しないため、ランニングコストを抑えられる点は魅力でしょう。
さらに、現金だけでなく有価証券での供託も可能なため、資金運用の柔軟性があります。
廃業時には供託金のほぼ全額を回収できるため、長期的に見ると費用対効果が高い選択肢といえます。
資金に余裕があり、保証協会の制約を受けずに自由度の高い経営を目指す場合には、営業保証金が適しているでしょう。
弁済業務保証金分担金の特徴
弁済業務保証金分担金は、宅建業者が「保証協会」に加入する際に納付する金銭で、金額は以下のとおりです。
対象 | 金額 |
主たる事務所(本店) | 60万円 |
その他の事務所(支店など) | 1拠点につき30万円 |
出典:公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会のご案内」
先の例と同じく、
- 本店:1店舗
- 支店:2店舗
をもった場合、必要な弁済業務保証金分担金は「合計120万円(60万円 + 30万円 × 2)」です。
弁済業務保証金分担金の特徴は、以下のとおり。
- 納付できるのは金銭のみ(有価証券不可)
- 納付先は保証協会
- 保証協会の入会金や年会費が別途必要
弁済業務保証金分担金は、営業保証金の代わりになります。
宅建業者は、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付することで、高額な営業保証金(本店1,000万円、支店500万円)の供託が免除されます。
弁済業務保証金分担金のメリット
弁済業務保証金分担金のメリットは、初期費用を大幅に削減できることです。
営業保証金の場合、本店で1,000万円が必要なのに対し、弁済業務保証金分担金は60万円の金額で済みます。
保証協会の入会金や諸費用を含めて100万円程度で開業できる場合もあるため、資金調達のハードルが大幅に下がります。(※2)
さらに、保証協会に加入することで、営業支援や各種研修の受講機会、経営相談サポートなど、充実したバックアップを受けることが可能です。(※3)
同業者とのネットワーク構築の機会も豊富で、情報交換や業務提携につながる可能性もあります。
開業資金に限りがある場合や、業界の知識やネットワークを積極的に活用したい新規参入者にとって、弁済業務保証金分担金は非常に魅力的な選択肢です。
廃業時には供託金部分の回収も可能なため、リスクも限定的といえるでしょう。
(※2)出典:公益社団法人 全日本不動産協会 埼玉県本部|入会までの流れ
(※3)出典:全宅連|宅建業開業までの流れ
不動産開業でどちらの供託金を選ぶべきか?

営業保証金と弁済業務保証金分担金のどちらを選ぶかは、個人の状況によって異なります。
具体的には、以下の点を考慮して判断するとよいでしょう。
考慮する点 | 詳細 |
初期費用の負担 | 弁済業務保証金分担金分のほうが金額が少なく、初期費用をおさえられる |
将来の事業拡大 | 営業保証金は高額だが、有価証券での供託も可能なため、将来的に支店を増やす予定があるときはメリットになる可能性も |
保証協会のサポート | 弁済業務保証金分担金を選ぶと、保証協会のサポートを受けられる |
現状や将来を考慮し、自身にあった選択をしましょう。
また、弁済業務保証金分担金を選ぶ場合、入会する保証協会には
- ハトマークの「全国宅地建物取引業保証協会(=全宅)」
- ウサギマークの「不動産保証協会(=全日)」
の2種類があります。
それぞれの違いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
https://iimon.co.jp/column/all-japan-real-estate-association-real-estate-guarantee-association-difference
不動産の供託金の支払いから開業までの流れ
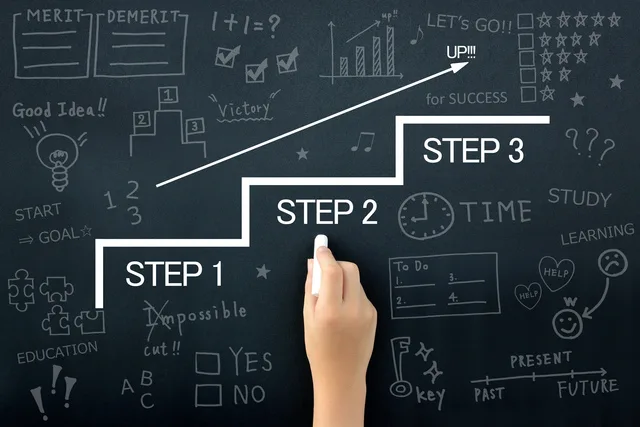
営業保証金と弁済業務保証金分担金のどちらを選択するかが決まったら、次は実際の手続きを進めていきます。
供託金の手続きは宅建業免許の取得と関わるため、正しい順序で進めることが重要です。
手続きの流れや必要書類、期限などは選択する供託金の種類によって異なるため、事前に詳細を把握しておくことで、スムーズな開業を実現できます。
ここでは、営業保証金と弁済業務保証金分担金それぞれの具体的な手続き方法について、ステップごとに詳しく解説していきます。
営業保証金の手続き
営業保証金の手続きは、宅建業免許の通知を受けたあとから開始できます。
具体的な流れは、以下のとおりです。
- 事務所所在地の都道府県知事から免許登録の通知(はがき)が届く
- 本店の最寄りの法務局または地方法務局、支局・出張所などの供託所で営業保証金を供託する
- 供託手続きが完了すると「供託書の写し」が交付される
- 免許登録を受けた行政機関に「供託書の写し」を届け出る
- 免許証が交付される
- 営業を開始する
流れは複雑ではありませんが、宅建業の免許登録を受けてから3カ月以内に、供託手続きと届出を完了する必要があります。(※4)
万が一、届出ができず事務所所在地の都道府県知事から催告が到達した場合は、その日から1カ月以内に届出しなければなりません。(※4)
催告がきても届出しない場合には、免許が取り消される可能性もあるので注意が必要です。
(※4)出典:岐阜県公式ホームページ「営業保証金関係の手続き」
弁済業務保証金分担金の手続き
弁済業務保証金分担金を選択する場合は、まず保証協会への加入が必要です。
主な保証協会には「全国宅地建物取引業保証協会(全宅・はとマーク)」と「不動産保証協会(全日・うさぎマーク)」があります。
手続きは、宅建業免許の通知を受けたあとから開始でき、以下の流れで進みます。
- 選択した保証協会に加入申請書を提出し、入会資格の審査を受ける
- 承認後、弁済業務保証金分担金・保証協会の入会金・年会費などの諸費用を納付する
- 保証協会が代行して法務局への供託、都道府県知事への届出を行う
- 届出先から「宅地建物取引業者免許証」が交付される
- 営業を開始する
入会審査がありますが、法務局への供託や都道府県知事への届出を代行してもらえるため、自身の手間を省くことが可能です。
不動産開業で勢いに乗るなら速いもんシリーズ

無事に開業できたら、そのあとは経営を安定化できるかが不安なポイントですよね。
不動産業の開業で経営を安定させるには、日々の業務の効率化が重要です。
(株)iimonが提供している「速いもんシリーズ」であれば、不動業における業務効率化を実現しやすくなります。
速いもんシリーズには、以下のような種類があります。
サービス名 | 特徴 |
不動産ポータルサイトへの入力作業を効率化 | |
賃貸物件の新着・更新情報の洗い出しを効率化 | |
ライバル会社の掲載状況を自動分析 | |
物件情報を1クリックでPDF・URL化 | |
賃貸物件情報の元付会社を簡単に特定 | |
売買・賃貸物件の募集状況をまとめて確認 | |
1サイトで複数サイトの物件検索が可能 | |
見積書をワンクリックで瞬時に作成 | |
入力間違い╱他社募集╱条件判定を1クリックで判定 |
なかでも「入力速いもん」は、物件登録作業を効率化できる便利なツールです。
具体的には、
- 業者間流通サイトの物件情報を「1クリック」で保存
- 物件情報入力画面へ「1クリック」で反映
といったように合計「2クリック」で、不動産ポータルサイトなどへの物件入力作業が完了するため「手間暇」「時間」など、業務負担になる原因を削減できます。
【事例】入力速いもん導入で入力時間50%削減!
実際に「入力速いもん」を導入した企業の事例を見ていきましょう。
賃貸マンション・アパートに強みをもつ「株式会社ファーストキー」では、以下のような課題を抱えており、業務に負担がかかっていました。
- 物件入力に時間を要し、残業も多い状態だった
- 自社HPに掲載する物件情報の更新が進まず、情報の鮮度に課題を感じていた
しかし「入力速いもん」導入で、以下のような成果を得られました。
- 物件情報入力にかかる時間=従来比50%以上削減!
- 残業=ほぼ”0”!
- タイムリーな情報更新を実現!
「課題解決において、文句のつけようのないサービスです」とのお声もいただきました。
まとめ
不動産開業において、供託金の支払いは宅地建物取引業法により義務づけられています。
この制度はおもに消費者保護を目的としており、高額な不動産取引におけるトラブルから消費者を守る役割を果たしているのです。
供託金には以下の2種類があり、どちらかを選択して納付する必要があります。
項目 | 営業保証金 | 弁済業務保証金分担金 |
供託先 | 直接法務局に供託 | 保証協会を通じて納付 |
金額(本店) | 1,000万円 | 60万円 |
金額(支店1拠点) | 500万円 | 30万円 |
納付方法 | 現金または有価証券 | 金銭のみ |
開業後の経営安定化には、業務効率化が重要です。
(株)iimonが提供している「速いもんシリーズ」などのツールを活用して、物件登録作業などの日々の業務を効率化し、時間と労力を削減しましょう。

iimon 編集部












